ユダ木工『森を知る研修』withたなべたたらの里 2025
ユダ木工は2022年から、カーボン・オフセット制度を利用して、CO2排出量の削減とともに次世代の山づくりを支援する新しい取り組みを模索しています。
そしてカーボン・オフセットを通して、素敵なご縁が生まれました。古くからたたら製鉄で栄えた歴史ある町、島根県雲南市吉田町で里づくり・山づくりプロジェクトに取り組まれている「たなべたたらの里」さんにご協力いただき、ユダ木工では毎年「森を知る研修」として、植林活動や山林見学などを実施しています。

▲ 山林部 Sさん(左)から今年度カーボン・オフセット記念の盾を受け取る代表 湯田(右)
カーボン・オフセットの取り組みについてはこちら ↓
山の姿を思い描いて
たなべたたらの里さんは、新しい林業のあり方を広く模索されている事業者のひとつです。前例のない実験的な山づくりにも取り組まれていて、昨年は、桐の早生樹の植林地や、クヌギと南天を組み合わせて育てている山を紹介していただきました。(昨年の「森を知る研修」はこちら)
戦後、日本には沢山のスギやヒノキが植林されました。スギやヒノキは古くから建材などに広く利用されてきた、私たちの暮らしに欠かせない木です。「たなべたたらの里」にも、沢山のスギ・ヒノキがあります。そんな山の一角で、今年の春はミズナラの苗を植樹されたそうです。研修に向かう道中で、山林部のSさんにお話を伺いました。
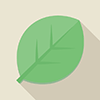
このあたりは、50~60年前に先人の手によってスギが植樹された山です。しかし、ここが本当にスギの木に適した土地だったのかは分かりません。よく観察してみると、この周囲にはナラの木が沢山生えているんです。
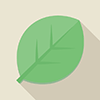
元々はナラの山だったのかもしれない、と私たちは考えました。それで、この斜面にミズナラを植樹しました。もっとも、次の50年先にはまた時代が変わりますから、そのときはまた別の考えがあり、別の木を植えるのかもしれません。

たしかに、スギ・ヒノキ以外の大きな木もあちこちに見られますね。そうやって観察からヒントを得て、山づくりをされているのですね。山が私たちに教えてくれているみたいで、素敵です。
(写真を撮りそびれてしまいました)
山に暮らす生き物と人
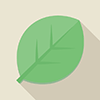
鹿に苗木を食べられてしまったりと、いわゆる「獣害」には我々も苦労しています。しかし「獣害」というのはあくまでも人間目線の話で、動物たちから見ると「獣害」は我々なのだろうとも思います。そうした視点を持ちつつ、山の生き物を観察する授業を企画しました。
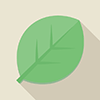
中学校との連携授業です。先生チーム・生徒チームに分かれて、それぞれ山の中に赤外線カメラを仕掛けます。そこに何が映っているか見てみよう。そして、たくさん動物が映っていたチームが優勝、というチャレンジです。
大スケールの仕事場。林業体験

林業体験では、山林部の若手、OさんとIさんがレクチャーしてくださり、木材の搬出を体験・見学しました。
